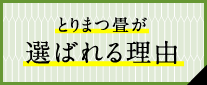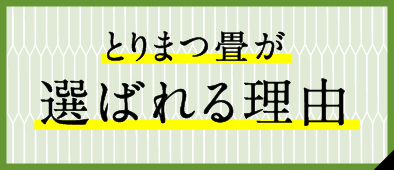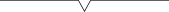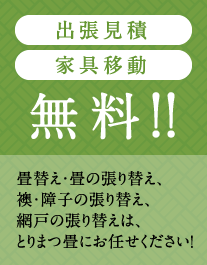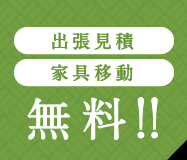和室で過ごす時間が好きな方のなかには、畳の穏やかな香りや独特な踏み心地を気に入っている方も多いのではないでしょうか。
なお、畳の品質や機能性はその畳に使われている素材や材料によって大きく変わります。本記事で畳の構造と素材・材料について、詳しく見ていきましょう。
また、国産(熊本産)と中国産の畳との価格の違いについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
畳の素材・材料【畳表(イ草)編】

畳は、畳表(たたみおもて)・畳床(たたみどこ)・畳縁(たたみべり)という3つの構造でできています。
畳表(たたみおもて)は畳を構成する部位のなかで、実際にお客様の肌に触れる部分です。露出面が大きいため、畳の見た目は畳表の品質によって決まると考えてもよいでしょう。
まずは、畳表に使われる素材、イ草(蘭草)と経糸(たていと)について説明します。
イ草
イ草を編みこんだ昔ながらの畳表は、現在でも主流のものです。天然の草がもたらす見た目や感触は、和のイメージそのものといえるでしょう。
イ草は単子葉植物イグサ科の植物で、おもに湿地などで自生しています。「燈芯草(トウシンソウ)」という別名で呼ばれることもあります。
天然素材のイ草には個体差があり、イ草の本数が多いもの、長くて太く、色合いが均一なもののほうが、品質が高いとされます。
畳表に使用されるのはイ草の茎部分です。先端の尖った細い茎を束ねて、畳表の素材として活用します。
畳を新しくした当初は緑色が濃く、少しずつ日焼けしていきます。このとき、質の良いイグサの場合は白っぽくきれいに焼けていくため、日焼けしてからもその表情の移り変わりを楽しむことができるでしょう。
畳の部屋で過ごすときに、「他の部屋よりも過ごしやすい」と感じる方もいるのではないでしょうか。和室がちょうど良い温度と湿度を保てるのは、イ草の性質によるものです。
イ草の内部には無数の気孔が空いていて、スポンジのような構造になっています。この構造により、室内の水分や嫌な臭い、有害物質を吸着することができるのです。
イ草にはほかにも、鎮静効果、リラックス効果、集中力向上にも影響するアロマ効果があるといわれています。フィトンチッドという匂いの成分が含まれており、森林浴で気分が良くなるのも、この成分が含まれているからです。
畳を新調するとなんとなく気持ちが良くなるのは、その見た目だけでなく匂いも大きく影響しているのでしょう。
麻や綿の経糸(たていと)
畳表の経糸(たていと)には、おもにマニラ麻糸、麻糸、綿糸などが使用されます。経糸のランクとしては、マニラ麻糸が最高級品で、次に麻糸、綿糸という順番です。
なお、経糸の本数や種類によって畳表のランクが変わってきます。綿糸と麻糸の両方を使用している場合、麻糸の比率が大きいほど耐久性が高いとされています。
経糸の織り方には、綿糸だけで織る「糸引き」、麻糸と綿糸を使用した「麻綿ダブル」、麻のみを使用した「麻ダブル」などがあります。使われている経糸の種類、等級については「JAS表示」に記載されていますので、購入時に確認してみるとよいでしょう。
畳の素材・材料【畳表(和紙)編】
畳の素材といえば天然素材のイ草ですが、最近は和紙を使用した「和紙表」も人気です。
和紙表はイグサの代わりに和紙を利用したもので、和紙を一本一本こよりにして編んでいます。イグサと比べると機能性重視であり、耐久性、日焼けしにくい、摩耗性に強い、カビの発生がしにくいといった特徴があります。
和紙表はカラーバリエーションも豊富で、昨今の和室作りでも注目を集めつつあります。和紙表を使うことで純和風ではなく、洋風和室にも合うモダンな仕上がりになるでしょう。
マンションの洋室やバリアフリーになっているお部屋などで広く活用されており、その美しい仕上がりは人気があります。また、劣化しにくく青々とした状態が長く続くため、あまり使わない部屋でも急な来客用として使用できるでしょう。
関連記事:
和紙畳って何?メリット・デメリットでわかる選び方のコツ|和室の豆知識
畳の素材・材料【畳表(樹脂)編】
近年は新しい畳表として樹脂素材の「樹脂表」が登場しており、その機能性の高さやデザイン性が注目を集めるようになりました。
樹脂表は変色や退色に強く、カビやダニの発生も抑えられます。汚れたときにも水拭きでお手入れできるため、小さな子どもがいる家庭やペットがいる家庭でも扱いやすい素材です。
カラーバリエーションも豊富であるため、和室の雰囲気を変えたい方、自分好みの和空間を演出したい方に向いています。
畳の素材・材料【畳床編】

続いては、畳本体の芯部分である「畳床(たたみどこ)」の素材を見ていきましょう。畳床に使われているおもな素材は、藁・ワラサンド畳床・建材床の3つです。
藁(わら)
従来の畳は、本畳床と呼ばれています。藁をいくつも重ねて作られており、踏み心地が良い点、吸湿性や弾力性に優れている点が魅力的です。
畳床は品質によってランクが分けられています。藁の密度が高いほど寿命が長く、品質に優れた高級品として扱われます。
最近は天然素材の藁より、安価な木材チップ・発泡スチロールの畳床を多く使うようになりました。これらの畳は藁の量が少ないため、本畳床よりも安価です。
新素材の畳床(1)ワラサンド畳床
ワラサンド畳床は、藁の間に発泡スチロールを挟んだ新素材の畳床です。軽くて湿気に強く、断熱性に優れています。
ワラサンド畳床は、発泡スチロールが使われている分、本畳床よりも安く入手可能です。藁も使用されているため、本畳床のような優しい足触りを楽しめます。
新素材の畳床(2)建材床
藁を用いず、発泡スチロールや木材チップのみで作られた畳床を建材床と呼びます。本畳床やワラサンド畳床とは異なり、踏み心地が硬めです。ただし、軽量で断熱性に優れており、安い価格で手に入れられます。
また、藁を使った畳はダニが発生しやすいため、メンテナンスに気を配らなくてはなりませんが、建材床の場合、ダニの心配が少ないのもメリットです。
畳を購入する際には、見た目だけではなく畳床の素材についても理解しておきましょう。住んでいる環境や予算に合わせて、最適な素材を選ぶのが望ましいです。
関連記事:
畳床(たたみどこ)の種類5選!素材別の特徴を解説
畳の素材・材料【畳縁編】

最後に、畳の縁に付けられた布部分である「畳縁(たたみべり)」の素材について説明します。
綿や麻の糸
畳縁は、畳表の端部分を保護する役割を果たします。従来の畳縁には、蝋引きして磨き上げた綿糸・麻糸が使われていました。しかし、現在は化学繊維が多く使われています。
畳縁には多数の素材・色・模様があります。かつては、身分に合わせて畳縁の模様や色を選ぶ必要がありましたが、現代ではそのような制約は一切ありません。
畳縁の種類によって和室の印象が大きく変わるので、ぜひ好みに合わせて選んでみてください。
関連記事:
畳縁(たたみべり)とは?選び方のポイントや「踏んではいけない」とされる理由を解説
畳表の価格は、イ草の産地・グレードによって決まる

国産のイグサのほとんどが、熊本県で生産されています。価格の安い中国産のイグサも広く使われていますが、国産のものと比較すると品質が落ちる点を理解しておきましょう。
コストパフォーマンスを重視するなら中国産、手触りや香りの良いもの、ささくれや色ムラのないものを選びたい方は、熊本産のなかから選んでみてください。
なお、畳の専門店であるとりまつ畳でも、複数のラインナップをご用意しております。
中国産・熊本産の畳の価格は以下のとおりです。
・中国産格安表:税抜3,500円~(税込3,850円~)
・中国産中級表:税抜6,800円~(税込7,480円~)
・中国産上級表:税抜8,800円~(税込9,680円~)
・中国産市松表:税抜6,800円~(税込7,480円~)
・熊本産格安表:税抜4,500円~(税込4,950円~)
・熊本産中級表:税抜8,800円~(税込9,680円~)
・熊本産上級表:税抜10,800円~(税込11,880円~)
・熊本産最高級表:税抜16,000円~(税込17,600円~)
まとめ
畳の構造は、畳表・畳床・畳縁の3つの部分で成り立つシンプルな構造です。各部分で使われている素材・材料によって、耐久性や吸湿性、断熱性など性能が変わってきます。
畳の種類を決める際は、畳表に使われている素材(イ草・和紙・樹脂)についても確認が必要です。住環境や用途を考慮しながら、自室に合うものを選択しましょう。
畳の専門店であるとりまつ畳では、さまざまな素材・価格帯の商品を多数取りそろえています。ベテランの職人が仕上げた高品質・低価格な畳を、この機会にぜひお試しください。
TEL:0120-211-021